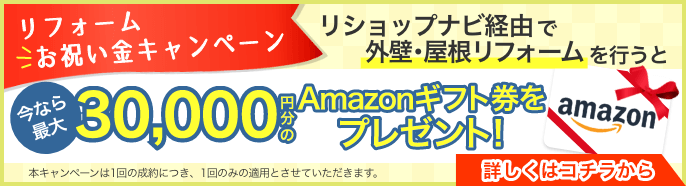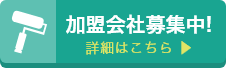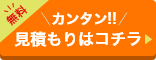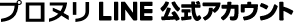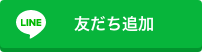申し込み
住宅財形で自宅をリフォーム!非課税の払い出し要件や注意点など解説
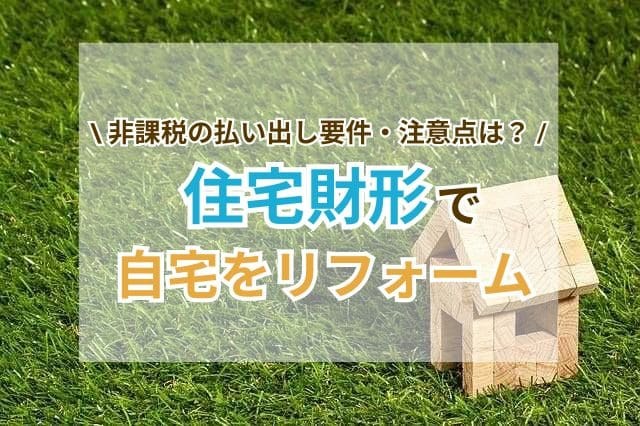
「自宅のリフォームに財形住宅貯蓄を使いたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。財形住宅貯蓄は、住宅の購入やリフォームに活用できる便利な貯蓄制度です。しかし、所定の条件を満たさないと資金を非課税で引き出せない可能性があります。非課税にならなかった場合、5年以上遡って税金を納めなければなりません。財形住宅貯蓄の資金を引き出す前に、非課税になる条件をしっかり確認しておきましょう。こちらの記事では、財形住宅貯蓄を非課税で引き出すための条件と、必要書類や手続き方法について解説します。
この記事の目次
- 1 財形住宅貯蓄とは
- 2 財形住宅貯蓄のメリット
- 3 財形住宅貯蓄のデメリット
- 4 財形住宅貯蓄をリフォームでお得に引き出す条件
- 5 【リフォーム箇所別】財形住宅貯蓄の課税・非課税の条件
- 6 リフォームで財形住宅貯蓄を引き出す際に必要な書類と手続き方法
- 7 リフォームで財形住宅貯蓄を引き出す際の注意点
- 8 リフォームに向けて財形住宅貯蓄を活用しよう
財形住宅貯蓄とは

財形住宅貯蓄は、主にマイホームの購入やリフォームなど、住宅に必要な資金を積み立てる貯蓄制度をいいます。
財形貯蓄制度を導入している企業の従業員は、基本的に利用可能です。
積立金額は給与やボーナスから天引きされ、勤務先が依頼する金融機関へ預けられます。
積立期間は一般的に5年以上必要です。
しかし、要件を満たしていれば、5年未満の積み立てでも資金を引き出せます。
財形住宅貯蓄のメリット

財形住宅貯蓄を利用するメリットは、主に以下の3つです。
普通預金よりも若干よい利率で貯蓄できる

財形住宅貯蓄は、一般的に銀行の普通預金口座より利率が高く設定されています。
例えば三菱UFJ銀行の場合、普通預金の利率は0.001%となり、財形住宅貯蓄は0.002~0.003%です。
「そこまで変わらないじゃないか」と思う方もいるでしょう。
確かに金利自体が低い時代のため、そこまで大きな差ではありません。
しかし、金利が高い分だけ資金は増えやすくなります。
普通預金に同じ金額を入れておくなら、少しでも高利率で資金が貯まりやすい財形住宅貯蓄を選ぶ方がよいでしょう。
非課税枠がある

財形住宅貯蓄には、非課税枠が設けられており、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を合わせて元利合計550万円まで非課税です。
通常、利子所得には税金が発生し、銀行預金で年2回程度受け取っている利息も、基本的には税金が引かれた後の金額が口座に入金されます。
非課税なら、本来支払うはずのお金が手元に残りやすくお得でしょう。
財形給付金制度により貯蓄のスピードアップに繋がる

財形給付金制度とは、主に財形貯蓄を奨励するための制度をいい、財形貯蓄を利用している従業員1人につき、上限10万円の掛金を会社が拠出し運用しています。
拠出金と運用益の合計額は、7年経過ごとに従業員へ一時金として支給され、財形住宅貯蓄を長く継続するほど会社から貰えるお金が増える仕組みです。
ただし、財形貯蓄制度はあっても財形給付金制度を導入していない会社もあります。
会社により導入状況は異なるため、勤務先の担当者に確認しましょう。
\考え中の方はこちらから!/
おすすめの業者をご紹介
財形住宅貯蓄のデメリット

財形住宅貯蓄のデメリットを2つ解説します。
金融商品によって元本割れの可能性がある

一般的に財形住宅貯蓄の積立金額は、ただ口座に眠らせるのではなく金融商品の資金として運用されます。
財形住宅貯蓄で取り扱う金融商品の中には、投資信託や生命保険など元本割れのリスクがある商品も存在しており、元本割れリスクを伴う金融商品の場合は、運用状況によっては損する可能性が0ではありません。
財形住宅貯蓄の取扱商品は、金融機関によって異なります。
絶対に元本割れしたくない人は、定期預金や国債などリスクが低い商品を選ぶとよいでしょう。
勤務先に財形住宅貯蓄がないと使えない

今後転職を行う場合、転職先では財形住宅貯蓄を実施していないということも考えられるでしょう。
転職先に財形住宅貯蓄がない場合は一旦解約するか、所定の中小企業団体を通じて1年のみ継続できる場合があります。
転職後も財形住宅貯蓄を継続するには、退職後2年以内に継続手続きが必要です。
財形住宅貯蓄をリフォームでお得に引き出す条件

財形住宅貯蓄は、住宅の購入・建設やリフォーム以外の用途で資金を引き出すと課税対象になります。
課税対象になると、基本的に非課税だった利子を5年前まで遡り、追納しなければなりません。
財形住宅貯蓄を非課税で引き出すには、以下のリフォーム要件を満たす必要があります。
【非課税対象となる基本要件(リフォーム)】
・リフォーム後の持ち家の床面積が50平方メートル以上である
・持ち家のリフォーム費用が75万円を超過する
・リフォームした持ち家に住宅財形の加入者本人(従業員)が住む
・リフォーム費用の2分の1以上が持ち家の居住部分の工事費であること
※居住用以外の箇所をリフォームするケース
床面積や工事費が基本要件に該当するか自分で判断するのは難しいため、リフォームを依頼する会社や建築士に確認しましょう。
【リフォーム箇所別】財形住宅貯蓄の課税・非課税の条件

リフォーム箇所や工事内容別、非課税となる「適格払い出し」についての説明です。
適格払い出しとは、主に財形住宅貯蓄の資金を非課税で引き出すための条件をいいます。
工事内容やリフォームする箇所によっては、適格払い出しと認められないことがあり、そのような場合、資金の引き出しに基本的に税金が発生してしまうため、必ず確認しておきたい条件です。
非課税になるリフォーム

非課税になる(適格払い出しと認められる)リフォーム箇所の例をご紹介します。
工事内容 | リフォーム箇所 |
|---|---|
増改築 | 屋根・外壁などの大規模な修繕 |
床または壁全部の修繕工事 | トイレ・風呂・キッチン・部屋・玄関など |
バリアフリー工事 | 通路の拡張、風呂・トイレの改修、手すりの増設など |
性能向上リフォーム | 省エネ工事 |
>>外壁に必要とされる補修の種類は?費用なども詳しく解説!
>>省エネ商品として受賞歴もあるガイナは、どんな塗料?特徴などを紹介!
>>熱伝導を抑える効果のある断熱塗料とは?費用や耐用年数も説明します!
非課税にするには大規模の模様替え・修繕があったことを証明する必要があります。
模様替え・修繕が大規模かどうかは建築士が判断するため、リフォームを依頼する会社や建築事務所へ問い合わせて確認しましょう。
建築士が適格払い出しの対象だと判断した場合は、「増改築等工事証明書」が発行されます。
増改築等工事証明書は資金引き出しの際に必要な書類のため、大切に保管しましょう。
\考え中の方はこちらから!/
おすすめの業者をご紹介
課税されるリフォーム

一般的に課税される(適格払い出しと認められない)リフォームの例は、以下の通りです。
・太陽光パネルのみ設置
・オール電化の導入
・親名義の実家のリフォーム
また、オール電化の導入については、場合により非課税と認められる可能性がありますが、非課税対象工事となるかは建築士の判断となります。
仮に財形住宅貯蓄の加入者本人が実家に住んでいても、基本的に親名義の実家の場合は要件外となるので、気を付けましょう。
適格払い出しの対象となるのは、一般的には加入者(従業員)名義の住宅のみです。
リフォームで財形住宅貯蓄を引き出す際に必要な書類と手続き方法

財形住宅貯蓄は、1回払い出し・2回払い出しで提出書類が若干異なるので、注意しましょう。
主に、1回払い出しはリフォーム後に資金を引き出すこと、2回払い出しはリフォーム前後に資金を引き出すことをいいます。
払い出し回数 | 必要書類 |
|---|---|
1回払い出し(リフォーム後) | ・住宅に関する工事請負契約書 |
2回払い出し(リフォーム前後) | ・工事請負契約書(リフォーム前に提出) |
※工事の費用が75万円を超えて100万円以下の金額となる場合は、「増改築等工事証明書」を「増改築等工事完了届」で代替して提出することも可能です。
財形住宅貯蓄を引き出す際の、基本的な手続き方法は以下になります。
1. 勤務先の担当者もしくは金融機関へ問い合わせる
2. 所定の申込用紙に記入および必要書類を準備
3. 指定された期日までに書類一式を提出
4. 資金が口座へ振り込まれる
書類を期日までにきちんと提出しないと、基本的に要件外(住宅取得やリフォーム以外)の払い出しと判断されてしまいます。
課税対象にならないよう、リフォームを依頼する会社と相談しながら早めに準備を進めましょう。
リフォームで財形住宅貯蓄を引き出す際の注意点

財形住宅貯蓄をリフォーム費用に使う際は、資金の引き出し方法に注意しましょう。
財形住宅貯蓄の資金の引き出し方は、主に3種類あります。
・一部払い出し
・全額払い出し
・口座解約
一部払い出しの金額は、残高の9割までしか引き出せません。
もしくは必要金額が残高の9割未満なら、必要な額のみ引き出すことが可能です。
また、リフォーム前に資金を引き出す場合は、一部払い出しのみとなります。
リフォーム後であれば、一般的には、一部払い出し・全額払い出し・口座解約のどれでも可能です。
リフォームに向けて財形住宅貯蓄を活用しよう

財形住宅貯蓄は、リフォーム費用のためにぜひ活用したい制度です。
普通預金よりも利率が高いことが多く、効率的にリフォーム資金を積み立てられるでしょう。
財形住宅貯蓄を非課税で引き出すには、リフォーム後の床面積や工事費用に関する定めがあります。
さらに、リフォーム箇所や工事内容により非課税にならない場合があるため、業者と相談しながら準備することが大切です。
>>外壁塗装の業者選びで失敗しないためには?
>>塗装業者が持っていると安心できる資格とは?業者の選び方のポイントも解説!
いつまでも快適なマイホームを保つために、計画的なリフォームを行いましょう。
最後に、今回の内容を簡単にまとめてみましたので、ご確認ください。
財形住宅貯蓄は、どんな用途で資金を引き出しても課税されないですか? |
|---|
用途によっては、課税される対象となりますので、気を付けましょう。 |
財形住宅貯蓄を引き出したい場合、リフォーム後の1回またはリフォーム前後の2回で資金を引き出す2つの方法がありますが、引き出しの際に必要な書類はどちらも同じですか? |
それぞれ提出する書類がいくつか異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。 |
財形住宅貯蓄の資金を引き出す方法は、リフォーム前・リフォーム後の場合それぞれ同じですか? |
資金を引き出す方法には種類があり、リフォーム前とリフォーム後で利用できる方法が異なります。 |
■この記事の編集者
|
無料
厳選された
地元の業者を手間なく徹底比較!
さっそく業者を探してみる

LINEお友達登録で
- 最新の塗装情報をお届け!
- LINE限定キャンペーンも開催!
関連記事
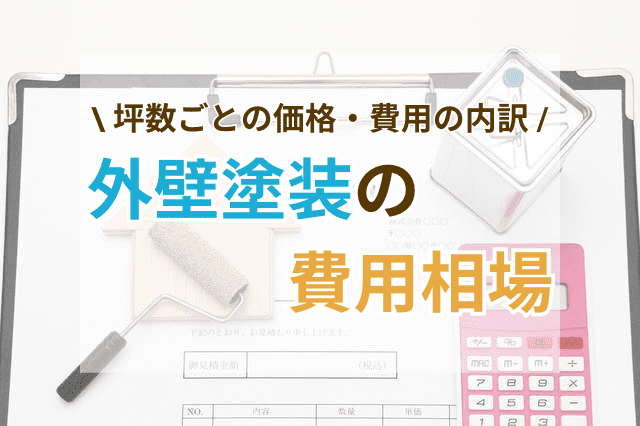
【2024年最新版】外壁塗装の坪数ごとの費用相場は?単価・適正価格を知ろう!
一般的な30坪の戸建て住宅の場合、外壁塗装の費用相場は60〜100万円ほどです。家の大きさや塗料の種類などが変わると、価格は大きく変動します。値段が高すぎても安...

外壁塗装には火災保険が適用される?実は台風や屋根の雨漏りにも対応!
住宅の火災保険は、火災だけでなく台風や大雪などの自然災害にも対応しています。また、外壁だけでなく屋根の雨漏りも適用範囲です。しかし、火災保険の種類によっては対応...

火災保険を使って屋根修理の費用負担を減らそう!利用の条件や申請方法も解説!
「屋根修理をしたいけど金額が高くなるのが心配」「台風で屋根修理が必要になった場合、何か安くなる方法はないの?」といった疑問をお持ちの方はいませんか?屋根修理をす...
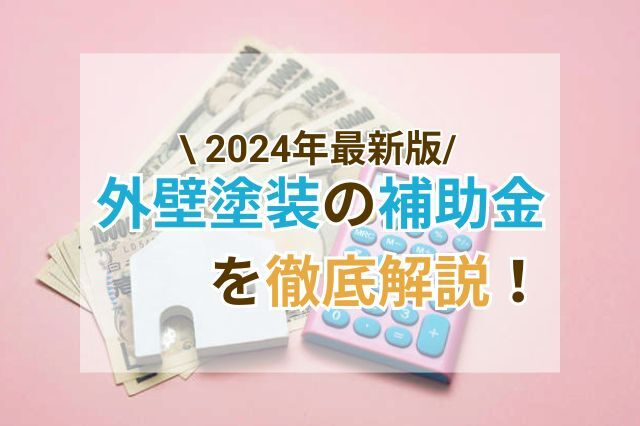
【2024年】外壁塗装の助成金・補助金を徹底解説!条件・申請方法や注意点も
外壁塗装のリフォームで、助成金や補助金を受け取れるケースがあることをご存じでしょうか?この記事では、戸建て住宅の外装リフォームで対象となりやすい助成金・補助金の...

屋根工事の種類や費用は?業者選びの注意点やポイントも解説!
「屋根の工事には、どんなものがあるのか知りたい」「どんな会社に依頼すればよいのだろう」屋根の補修を依頼する際に、どんなリフォームを依頼するべきかわからない方も多...